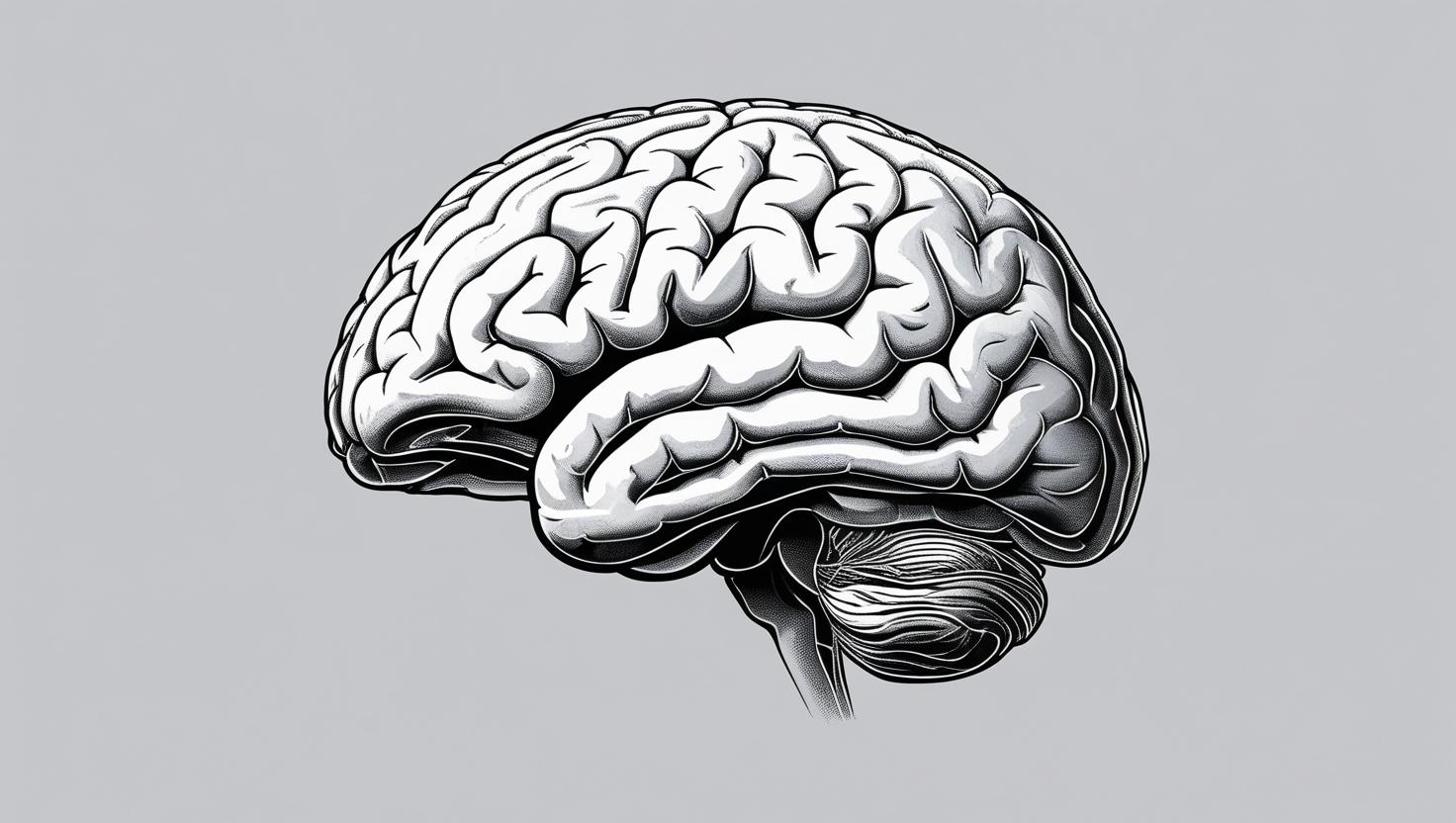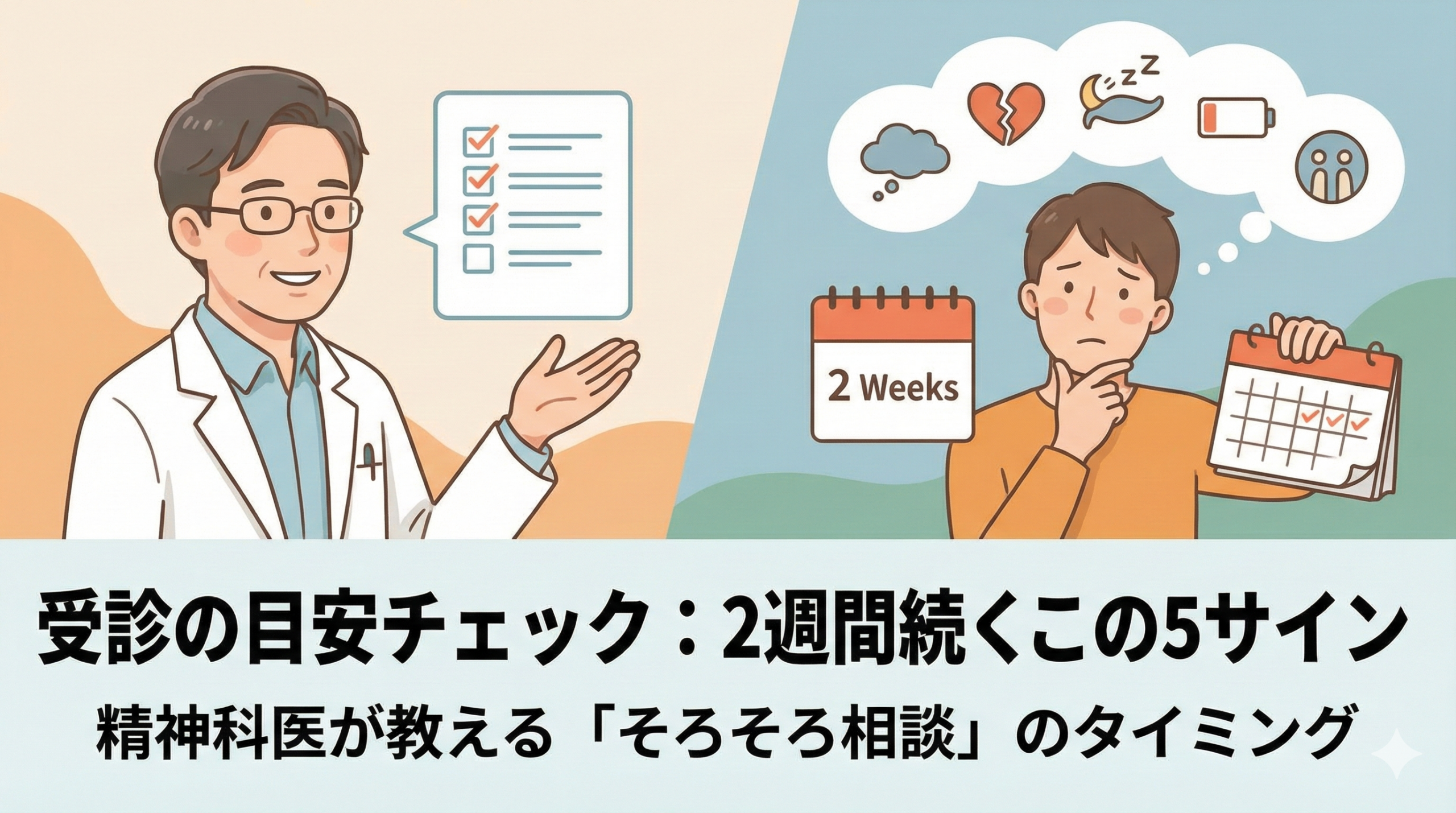2025年10月20日

「なんであの人は平気そうなのに、私はこんなにしんどいんだろう…」
精神科外来でよく聞かれる言葉です。同じ職場、同じような仕事量なのに、ケロッとしている人もいれば、心身ともに疲弊してしまう人もいる。この違いは、単なる「心の強さ」の問題なのでしょうか?
答えはNOです。ストレスに対する反応の個人差は、脳内の神経伝達物質のバランスと、その調整システムの違いによって科学的に説明できます。
実は、ストレスに対する反応の個人差は、脳内の神経伝達物質のバランスと、その調整システムの違いによって科学的に説明できるのです。今回は、精神科医として日々患者さんと向き合う中で見えてきた「ストレスで心が疲れる本当のメカニズム」について、最新の神経科学の知見を交えながら解説します。
第1段階:数秒〜数分「警報が鳴り響く」
ストレスを感じた瞬間、まず最初に反応するのがノルアドレナリンです。
例えば、上司から急に「ちょっといいか」と呼ばれた瞬間を想像してください。心臓がドキッとして、背筋がピンと伸びる。これがノルアドレナリンの仕業です。青斑核という脳の部位から急速に放出され、以下のような変化を引き起こします:
- 心拍数の上昇
- 血圧の上昇
- 覚醒度の急上昇
- 注意力の一点集中
これ自体は悪いことではありません。むしろ、危機に対応するための「戦うか逃げるか(fight or flight)」反応として、私たちの祖先が生き延びるために獲得した大切なシステムです。
第2段階:数分〜数十分「感情の揺らぎ」
次に反応するのが、セロトニンとドーパミンといったモノアミン系の神経伝達物質です。
セロトニンは特に興味深い物質で、「幸せホルモン」として知られていますが、実はストレス時には複雑な働きをします:
- 前頭前野では→不安を抑える方向に働く
- 扁桃体では→逆に不安を増強することも
- 全体としては→ストレス反応を「調整」する役割
一方、ドーパミンは報酬系に関わる物質で、ストレス直後は一時的に増加しますが、その後減少するという二相性の反応を示します。これが「やる気が出たり出なかったりする」原因の一つです。
第3段階:10分以降〜数時間「記憶と学習への影響」
最後に、グルタミン酸という興奮性の神経伝達物質が増加し、特に前頭前野や海馬(記憶の中枢)でシナプス伝達が強化されます。
McEwen & Akil (2020)の研究によれば、慢性的なストレスはコルチゾール(ストレスホルモン)の持続的な分泌を引き起こし、遺伝子発現にまで影響を与えることが報告されています。
McEwen BS, Akil H. (2020) “Revisiting the Stress Concept: Implications for Affective Disorders” Journal of Neuroscience, 40(1): 12-21.
つまり、強いストレスは文字通り「脳の配線を変えてしまう」可能性があるのです。
ユーストレス(良いストレス)の特徴
適度なストレスは、実はパフォーマンス向上に役立ちます:
神経伝達物質の変化:
- ノルアドレナリン:一過性の適度な上昇→集中力UP
- ドーパミン:報酬予測が活性化→モチベーションUP
- セロトニン:適切な調整機能を発揮
- グルタミン酸:学習・記憶の促進
具体例:
- 締切前の適度なプレッシャー
- スポーツの試合前の緊張
- 新しいチャレンジへの不安と期待
これらのストレスは、終わった後に「やってよかった」「成長できた」という感覚をもたらします。
ディストレス(悪いストレス)の特徴
一方、過剰または慢性的なストレスは脳にダメージを与えます:
神経伝達物質の変化:
- ノルアドレナリン:慢性的な過剰分泌→枯渇
- ドーパミン:報酬系の機能低下→無気力
- セロトニン:調整機能の破綻→うつ・不安
- グルタミン酸:過剰な興奮→神経毒性
Popoli et al. (2011)の研究では、慢性ストレスがシナプス可塑性を損ない、前頭前野と海馬の神経回路に構造的変化をもたらすことが示されています。
エビデンス:Popoli M, Yan Z, McEwen BS, Sanacora G. (2011) “The Stressed Synapse: The Impact of Stress and Glucocorticoids on Glutamate Transmission” Nature Reviews Neuroscience, 13(1): 22-37.
具体例:
- 終わりの見えない過重労働
- 継続的な人間関係のストレス
- 経済的不安の長期化
うつ病や不安障害の治療でよく使われるSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)。「飲み始めてすぐには効かない」「最初はむしろ不安が強くなることがある」という話を聞いたことはありませんか?
実は、SSRIは効果が現れるまでに2〜6週間かかることが一般的です。これには深い神経科学的な理由があります。
投与初期(数日〜1週間):セロトニンは増えるのに効果が出ない理由
SSRIを飲むと、シナプス間隙のセロトニン濃度は急激に上昇します。「それならすぐ効くのでは?」と思うかもしれませんが、実はそう単純ではありません。
最初の数日は、脳が「セロトニンが増えすぎないように」と自己調節機能を発揮し、一時的に効果が現れません。さらに、この時期には扁桃体や延長扁桃体(BNST)のCRF神経回路が刺激され、一時的に不安が増強してしまうこともあります。「薬を飲んでるのに悪化した!」と感じる患者さんがいるのはこのためです。
適応期(2〜6週間):脳が本当に変わり始める
継続的にSSRIを服用すると、以下のような段階的な変化が起きます:
1. セロトニン系の適応的変化
Fritze et al. (2017)のメタ分析では、慢性的なSSRI投与により5-HT1A自己受容体の感受性が低下し、これによって背側縫線核の「ブレーキ」が緩み、末端でのセロトニン放出が持続的に増加することが示されています。
エビデンス:Fritze S, Spanagel R, Noori HR. (2017) “Adaptive Dynamics of the 5-HT Systems Following Chronic Administration of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors: A Meta-Analysis” Journal of Neurochemistry, 142(5): 747-755.
2. シナプス密度の増加
2023年の画期的な研究で、SSRIが実際に脳のシナプス(神経のつながり)の密度を増やすことが、生きている人間の脳で直接確認されました。
Johansen et al. (2023)は、健康な成人にエスシタロプラム(SSRI)を投与し、PETスキャンでシナプス密度を測定しました。その結果、3〜5週間の服用で前頭前野や海馬のシナプス密度が有意に増加することが示されました。つまり、SSRIは「神経のつながりを増やす」ことで効果を発揮するのです。
エビデンス:Johansen A, Armand S, Plavén-Sigray P, et al. (2023) “Effects of Escitalopram on Synaptic Density in the Healthy Human Brain: A Randomized Controlled Trial” Molecular Psychiatry, 28(10): 4272-4279.
3. 感情処理の変化
SSRIのもう一つの重要な作用は、「物事の見方」を少しずつポジティブに変えていくことです。
Harmer & Cowen (2013)の認知神経心理学的研究では、SSRIが感情の受け止め方や記憶の仕方に影響を与え、ネガティブな情報への注意が減り、ポジティブな情報への感受性が高まることが示されています。これは気分が良くなる「前」から始まり、徐々に主観的な気分の改善につながります。
エビデンス:Harmer CJ, Cowen PJ. (2013) “‘It’s the Way That You Look at It’–a Cognitive Neuropsychological Account of SSRI Action in Depression” Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences, 368(1615): 20120407.
4. その他の神経生物学的変化
- 神経栄養因子の増加:BDNFなどが増え、神経細胞の成長を促進
- 炎症の抑制:炎症性サイトカインが低下
- 神経回路の再構築:前頭前野-辺縁系の接続が改善
これらの変化には時間がかかるため、「効果を実感するまで最低2〜4週間、完全な効果には6〜8週間は続けてください」とお伝えしています。早期に服薬を中断すると、脳の適応プロセスが完了せず、本来得られるはずの効果が得られません。焦らず、医師の指示通りに薬を続けることが最も大切です。
セロトニンは非常に複雑な働きをする物質です。「セロトニンを増やせば幸せになれる」という単純な話ではありません。
部位による作用の違い
不安を抑制する部位:
- 前頭前野(特に前頭前皮質)
- 背側縫線核の5-HT1A自己受容体
不安を増強する可能性がある部位:
- 扁桃体の特定の回路
- 延長扁桃体(BNST)のCRF産生神経
Marcinkiewcz et al. (2016)の重要な研究では、扁桃体のセロトニンが不安と恐怖を促進する回路を活性化させることが示されました。この発見は「セロトニン=幸せ」という単純な図式を覆す画期的なものでした。
エビデンス:Marcinkiewcz CA, Mazzone CM, D’Agostino G, et al. (2016) “Serotonin Engages an Anxiety and Fear-Promoting Circuit in the Extended Amygdala” Nature, 537(7618): 97-101.
受容体サブタイプによる違い
セロトニン受容体は14種類以上のサブタイプがあり、それぞれ異なる作用を持ちます:
- 5-HT1A受容体:主に抗不安作用
- 5-HT2A受容体:興奮性、時に不安増強
- 5-HT2C受容体:食欲や睡眠に関与
だからこそ、「セロトニンのバランス」が重要なのです。
1. ストレスの種類を見極める
まず、今あなたが感じているストレスが「ユーストレス」なのか「ディストレス」なのかを判断しましょう:
ユーストレスのサイン:
- 終わりが見えている
- 自分でコントロールできる部分がある
- 成長の機会と感じられる
ディストレスのサイン:
- 慢性的で終わりが見えない
- コントロール感がない
- 消耗感ばかりで達成感がない
2. セロトニンを整える生活習慣
朝の日光浴(15-30分)
- セロトニン合成のスイッチをON
- 体内時計のリセット
リズム運動
- ウォーキング、ジョギング、ダンス
- 一定のリズムがセロトニン神経を活性化
Noetel et al. (2024)のメタ分析によれば、運動はうつ病に対して抗うつ薬や心理療法と同等の効果を持つことが、150以上の研究(14,170人)の分析から示されています。推奨は週150分の中等度運動(ウォーキングなど)ですが、週に2〜3回、30分程度から始めて、徐々に増やすのが現実的です。
エビデンス:Noetel M, Sanders T, Gallardo-Gómez D, et al. (2024) “Effect of Exercise for Depression: Systematic Review and Network Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials” BMJ, 384: e075847.
腸内環境の改善
- セロトニンの90%は腸で作られる
- 発酵食品、食物繊維を意識的に
3. ノルアドレナリンの暴走を防ぐ:呼吸法と瞑想
深呼吸・呼吸法の科学的根拠
呼吸法は、交感神経系の過剰な活性化を抑え、ノルアドレナリンの暴走を防ぐ最も手軽で効果的な方法の一つです。
Fincham et al. (2023)のメタ分析では、呼吸法がストレスと精神的健康に有効であることが、ランダム化比較試験のレビューで示されています。心拍数や血圧の低下、主観的ストレスの軽減をもたらし、スマートフォンアプリを使ったガイド付き呼吸も効果的であることが複数の研究で確認されています。
エビデンス:Fincham GW, Strauss C, Montero-Marin J, Cavanagh K. (2023) “Effect of Breathwork on Stress and Mental Health: A Meta-Analysis of Randomised-Controlled Trials” Scientific Reports, 13(1): 432.
推奨される呼吸法
- 4:6呼吸法:4秒かけて吸って、6秒かけて吐く。どちらも鼻呼吸かつ腹式呼吸で。
- 6回/分のペース呼吸:ゆっくりとしたリズムで心拍変動を最適化
- アプリガイド呼吸:スマートフォンアプリを使ったガイド付き呼吸も有効
瞑想・マインドフルネス
Szuhany & Simon (2022)の不安障害レビューでは、マインドフルネスベースのストレス低減法(MBSR)やマインドフルネス認知療法(MBCT)が、短期的な不安・ストレス軽減に有効であり、認知行動療法(CBT)と同等の効果を持つことが示されています。
エビデンス:Szuhany KL, Simon NM. (2022) “Anxiety Disorders: A Review” JAMA, 328(24): 2431-2445.
段階的なタスク分解
大きな課題を小さなステップに分けることで、ストレス負荷を軽減できます。これは認知行動療法(CBT)のコア技法として推奨されています。
- 大きなストレスを小さく分割
- 達成可能な目標設定
- 各ステップでの達成感を味わう
4. ドーパミンを枯渇させない:報酬系の健全な維持
小さな達成感の積み重ね
日々の小さな目標達成が、報酬系の活性化を促し、ドーパミン系の健全な維持に貢献します。慢性的なストレスはドーパミン系を枯渇させますが、適切な報酬体験はその機能を維持します。
- ToDoリストの活用とチェック
- 進捗の可視化
- 達成した項目を振り返る習慣
報酬の先延ばし訓練
すぐの満足より長期的な満足を選ぶ練習は、自己制御力の向上とドーパミン系の適応的活性化に関連します。
- 即座の報酬ではなく、努力後の報酬を得る習慣
- マシュマロテストの大人版:長期的目標の設定
- 達成プロセスそのものを楽しむ姿勢
以下のような症状が2週間以上続く場合は、専門医への相談を検討してください:
中等度以上のうつ・不安症状
Simon et al. (2024)のJAMAレビューでは、以下のような客観的指標が専門家への相談基準として推奨されています:
- PHQ-9スコア10以上:中等度以上のうつ症状
- GAD-7スコア10以上:中等度以上の不安症状
エビデンス:Simon GE, Moise N, Mohr DC. (2024) “Management of Depression in Adults: A Review” JAMA, 332(2): 141-152.
身体症状
- 不眠または過眠
- 食欲の極端な変化
- 原因不明の体の痛み
- 極度の疲労感
精神症状
- 持続的な不安や恐怖
- 興味や喜びの喪失
- 集中力の著しい低下
- 死にたい気持ち、自殺念慮や計画
- 精神病症状(幻覚・妄想)の出現
行動面の変化と機能障害
- 社会的引きこもり
- アルコールや薬物への依存
- 自傷行為
- 日常生活への重大な支障(仕事・学業・家事ができない)
- 初期治療で改善がみられない(セルフケアや一次医療で2週間以上変化なし)
「もう少し頑張れば」と我慢し続けることは、脳の神経伝達物質のバランスをさらに崩し、回復を困難にします。特に自殺念慮や精神病症状、日常生活への重大な支障が認められる場合は、緊急性が高いため、すぐに専門医(精神科医・心療内科医)への相談が必要です。早期の専門的介入が、最も効果的な治療につながります。
ストレスで心が疲れる本当の理由は、脳内の神経伝達物質のバランスが崩れ、その調整システムが機能不全を起こすことにあります。
- ストレス反応は段階的:ノルアドレナリン→セロトニン/ドーパミン→グルタミン酸
- 良いストレスと悪いストレスの違い:一過性 vs 慢性、コントロール可能 vs 不可能
- セロトニンの二面性:部位と受容体により作用が異なる
- 薬の効果には時間がかかる:脳の適応には2〜6週間必要、シナプス密度の変化や感情処理の最適化が鍵
- 科学的根拠のあるセルフケア:呼吸法、瞑想、運動、タスク分解、小さな達成感の積み重ね
- 専門家相談の基準:PHQ-9≥10、GAD-7≥10、自殺念慮、精神病症状、機能障害
「心の強さ」は生まれつきのものではありません。脳の仕組みを理解し、科学的根拠のある対処法を身につけることで、誰もがストレスと上手に付き合えるようになります。
一人で抱え込まず、必要な時は専門家の力を借りることも、賢明な選択です。あなたの脳は、適切なサポートがあれば必ず回復する力を持っています。
監修・執筆者
片山 渚 医師
五反田ストレスケアクリニック院長
- ✓ 精神保健指定医
- ✓ 日本医師会認定産業医
- ✓ 産業保健法務主任者(メンタルヘルス法務主任者)
- ✓ 健康経営アドバイザー
大学病院から民間病院まで幅広い臨床経験を活かし、患者さんが安心して治療を継続できるよう、わかりやすい情報提供を心がけています。神経科学の最新知見を日常診療に活かし、エビデンスに基づいた治療を実践しています。
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の症状や状況に対する医学的アドバイスではありません。医療に関する決定は、必ず医師と相談の上で行ってください。本記事の情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当院は責任を負いかねます。
参考文献
- McEwen BS, Akil H. (2020) “Revisiting the Stress Concept: Implications for Affective Disorders” Journal of Neuroscience, 40(1): 12-21. DOI: 10.1523/JNEUROSCI.0733-19.2019
- Marcinkiewcz CA, Mazzone CM, D’Agostino G, et al. (2016) “Serotonin Engages an Anxiety and Fear-Promoting Circuit in the Extended Amygdala” Nature, 537(7618): 97-101. DOI: 10.1038/nature19318
- Popoli M, Yan Z, McEwen BS, Sanacora G. (2011) “The Stressed Synapse: The Impact of Stress and Glucocorticoids on Glutamate Transmission” Nature Reviews Neuroscience, 13(1): 22-37. DOI: 10.1038/nrn3138
- Noetel M, Sanders T, Gallardo-Gómez D, et al. (2024) “Effect of Exercise for Depression: Systematic Review and Network Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials” BMJ, 384: e075847. DOI: 10.1136/bmj-2023-075847
- Simon GE, Moise N, Mohr DC. (2024) “Management of Depression in Adults: A Review” JAMA, 332(2): 141-152. DOI: 10.1001/jama.2024.5756
- Fritze S, Spanagel R, Noori HR. (2017) “Adaptive Dynamics of the 5-HT Systems Following Chronic Administration of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors: A Meta-Analysis” Journal of Neurochemistry, 142(5): 747-755. DOI: 10.1111/jnc.14114
- Johansen A, Armand S, Plavén-Sigray P, et al. (2023) “Effects of Escitalopram on Synaptic Density in the Healthy Human Brain: A Randomized Controlled Trial” Molecular Psychiatry, 28(10): 4272-4279. DOI: 10.1038/s41380-023-02285-8
- Harmer CJ, Cowen PJ. (2013) “‘It’s the Way That You Look at It’–a Cognitive Neuropsychological Account of SSRI Action in Depression” Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences, 368(1615): 20120407. DOI: 10.1098/rstb.2012.0407
- Fincham GW, Strauss C, Montero-Marin J, Cavanagh K. (2023) “Effect of Breathwork on Stress and Mental Health: A Meta-Analysis of Randomised-Controlled Trials” Scientific Reports, 13(1): 432. DOI: 10.1038/s41598-022-27247-y
- Szuhany KL, Simon NM. (2022) “Anxiety Disorders: A Review” JAMA, 328(24): 2431-2445. DOI: 10.1001/jama.2022.22744