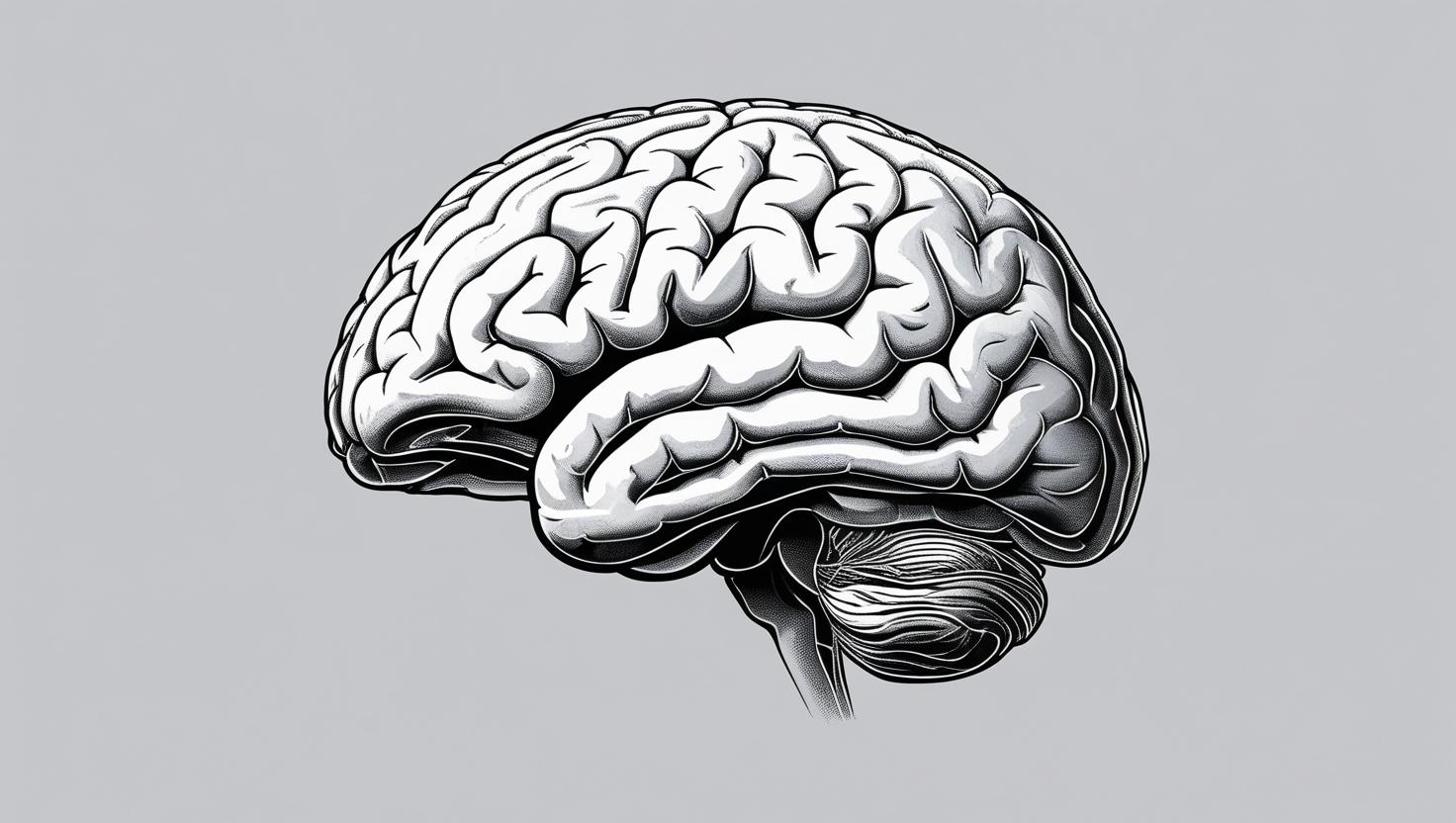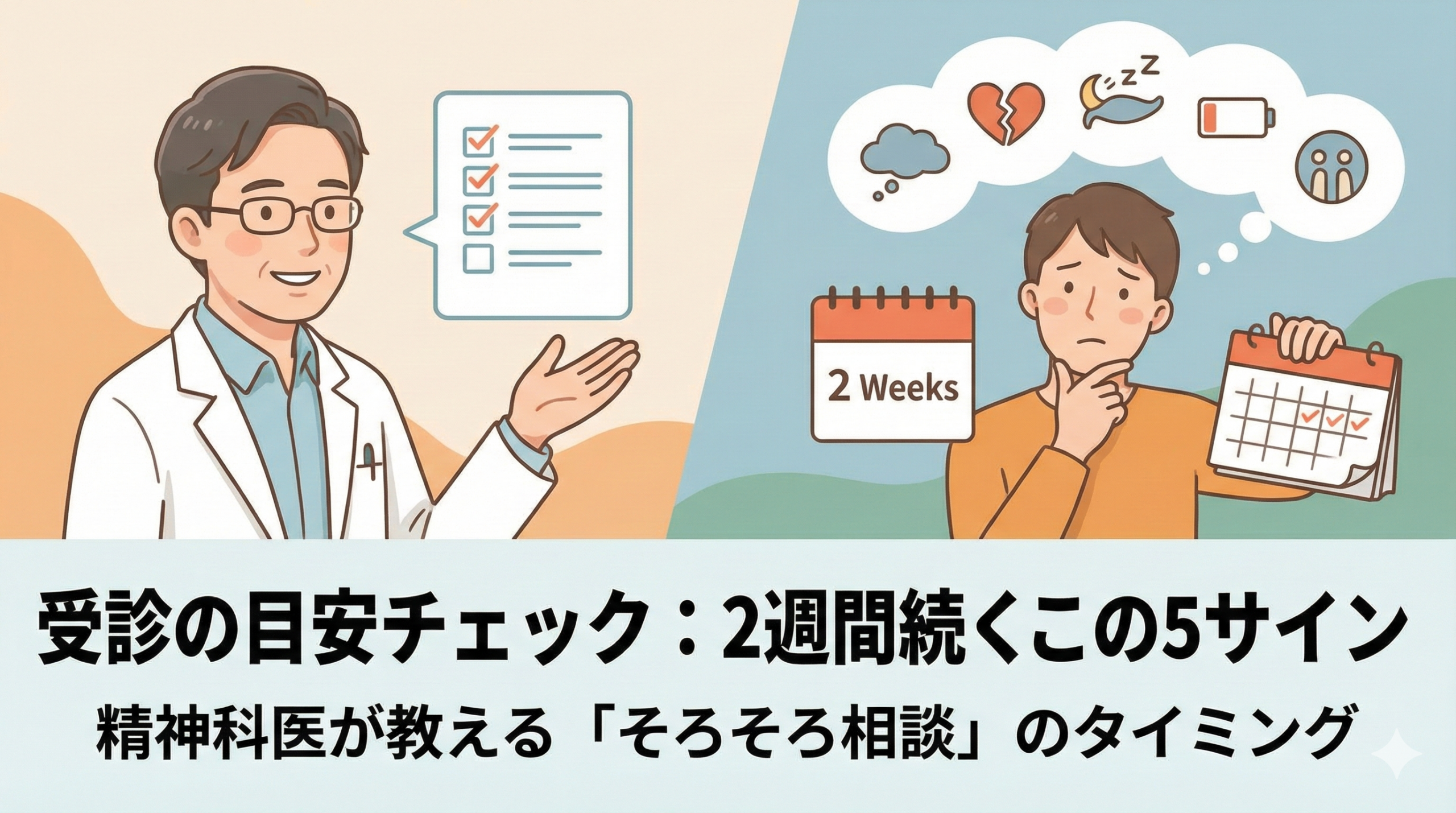2025年8月18日

「同じ職場で働いているのに、なぜ私だけこんなにストレスを感じるのか」「家族は平気なのに、自分だけが辛い」-このような悩みを抱えていませんか?実は、同じ状況でも人によってストレス反応が大きく異なることは、科学的に証明されています。
精神科医として多くの患者さんと接する中で、ストレスの感じ方の個人差は、性格の問題ではなく、遺伝的要因、幼少期の体験、現在の環境など、複雑な要因が絡み合って生まれることを実感しています。今回は、ストレスの原因と個人差について、最新の研究を交えて詳しく解説します。
ストレッサー(ストレスの原因)は、大きく外的ストレッサーと内的ストレッサーに分類されます。これらを理解することで、自分のストレスの源を特定し、適切な対処法を見つけることができます。
外的ストレッサーは、個人の外部環境から生じるストレス要因です。主なものを詳しく見ていきましょう。
経済的ストレスの具体例:
例:住宅ローンの返済、子どもの教育費、医療費の負担、失業や転職による収入減、老後資金の不安、物価上昇による生活費の圧迫
研究によると、経済的ストレスはHPA系を慢性的に活性化させ、うつ病や不安障害のリスクを2〜3倍高めることが分かっています。特に、借金がある場合は自殺念慮のリスクも上昇します。
- 量的負荷:長時間労働、過重な業務量、厳しい締め切り
- 質的負荷:責任の重さ、困難な意思決定、高度な専門知識の要求
- 対人関係:上司との関係、同僚との競争、パワハラ・セクハラ
- キャリア不安:昇進の停滞、雇用の不安定性、スキルの陳腐化
日本の調査では、約40%の労働者が仕事を「非常にストレスフル」と感じており、特に30〜40代の中間管理職層でストレスレベルが高いことが報告されています。

人間関係のストレスは、以下のような形で現れます:
- 夫婦・パートナー間の葛藤(価値観の相違、コミュニケーション不足)
- 親子関係の問題(子育ての悩み、親の介護、世代間の価値観の違い)
- 友人関係の悩み(裏切り、嫉妬、距離感の難しさ)
- 近隣トラブル(騒音、ゴミ問題、境界線の争い)
物理的環境もストレスの重要な源となります:
- 騒音:交通騒音、工事音、隣人の生活音(70dB以上で健康影響)
- 過密:満員電車、狭い住環境、プライバシーの欠如
- 気候:猛暑、厳寒、日照不足(季節性うつ病のリスク)
- 大気汚染:PM2.5、花粉、化学物質への暴露
内的ストレッサーは、個人の認知、思考パターン、身体状態から生じるストレス要因です。
ストレスを増幅させる思考パターン:
例:「失敗したら終わりだ」(破局的思考)、「みんな私を嫌っている」(読心術)、「いつも失敗する」(過度の一般化)、「完璧でなければ価値がない」(全か無か思考)
これらの認知の歪みは、実際の状況以上にストレス反応を強めることが分かっています。認知行動療法では、これらの思考パターンを修正することでストレスを軽減します。
特定の性格特性は、ストレス感受性を高めます:
- 神経症傾向:不安や心配を感じやすい
- 完璧主義:高すぎる基準を自分に課す
- タイプA行動パターン:競争的、せっかち、攻撃的
- 内向性:社会的刺激に対して疲れやすい
身体的・精神的健康問題は、それ自体がストレッサーとなります:
- 慢性疼痛(腰痛、頭痛、関節痛)
- 慢性疾患(糖尿病、心臓病、がん)
- 睡眠障害(不眠症、睡眠時無呼吸症候群)
- 精神疾患(うつ病、不安障害、PTSD)
なぜ同じストレッサーに対して、人によって反応が異なるのでしょうか?その答えは、遺伝と環境の複雑な相互作用にあります。
研究により、以下の遺伝子多型がストレス感受性に影響することが分かっています:
- FKBP5遺伝子:コルチゾール受容体の感受性を調整(変異があるとストレス反応が過剰に)
- COMT遺伝子:ドーパミンの分解速度に影響(Val/Val型は高ストレス下でパフォーマンス低下)
- 5-HTTLPR:セロトニントランスポーター遺伝子(S型はストレスでうつ病リスク上昇)
- BDNF遺伝子:脳由来神経栄養因子(Val66Met多型でストレス脆弱性)
遺伝的要因は変更できませんが、「運命」ではありません。環境要因や生活習慣の改善により、遺伝的リスクを大幅に軽減できることが証明されています。
ACE(Adverse Childhood Experiences)研究により、幼少期の逆境体験が成人後のストレス反応に大きく影響することが明らかになっています。
- 虐待:身体的、精神的、性的虐待
- ネグレクト:身体的、情緒的ネグレクト
- 家庭機能不全:DV目撃、物質乱用、精神疾患、離婚、犯罪
ACEスコアが4以上の人は、0の人と比較して:
- うつ病リスクが4.6倍
- 自殺企図リスクが12.2倍
- アルコール依存症リスクが7.4倍
幼少期の慢性的ストレスは:
- HPA系の過剰反応性を引き起こす
- コルチゾール受容体のエピジェネティックな変化を生じさせる
- 海馬の発達を阻害し、ストレス調整能力を低下させる
現在の生活環境も、ストレス反応に大きく影響します。
- 社会的支援:家族、友人、同僚からのサポート
- 経済的安定:十分な収入と貯蓄
- 健康的な生活習慣:規則的な運動、良質な睡眠、バランスの取れた食事
- コーピングスキル:問題解決能力、感情調整スキル
- 意味や目的の感覚:人生の意義、スピリチュアリティ
- 社会的孤立:孤独、支援ネットワークの欠如
- 不健康な生活習慣:運動不足、睡眠不足、偏った食事
- 物質使用:アルコール、タバコ、薬物への依存
- 慢性的な時間圧:常に急いでいる、余裕のない生活
ハーバード大学の発達センターは、ストレスを3つのカテゴリーに分類しています。この分類を理解することで、どのようなストレスが有害で、どのようなストレスが成長につながるかを判断できます。
短期的で軽度から中等度のストレス反応で、健康的な発達に必要なものです。
ポジティブストレスの例:
例:初めての登校、予防接種、新しい仕事の初日、試験、スポーツの試合、初デート
特徴:
- HPA系の一時的な活性化
- サポートがある環境で経験される
- レジリエンス(回復力)を育む
- 成長と学習の機会となる
より深刻だが時間限定的なストレス反応で、適切なサポートがあれば回復可能です。
耐容ストレスの例:
例:親の死、離婚、重大な病気やケガ、自然災害の経験、失業
回復の条件:
- 信頼できる大人や支援者の存在
- 時間の経過とともに強度が減少
- 適切な治療やカウンセリング
- 健康的な対処メカニズムの活用
長期的で強烈なストレス反応で、適切なサポートがない状態で継続します。
毒性ストレスは、脳の構造と機能に永続的な変化をもたらし、生涯にわたる健康問題のリスクを高めます。早期の介入が極めて重要です。
毒性ストレスの原因:
- 慢性的な虐待やネグレクト
- 極度の貧困
- 家庭内暴力への長期暴露
- 戦争や紛争地域での生活
- 親の重度の精神疾患や物質依存
毒性ストレスの影響:
- 脳の発達:前頭前皮質の発達遅延、海馬の萎縮
- 免疫系:慢性炎症、自己免疫疾患のリスク上昇
- 心血管系:高血圧、心疾患のリスク上昇
- 精神的健康:うつ病、不安障害、PTSD、物質依存のリスク上昇
日本社会には、独特の文化的背景に基づくストレス要因があります。これらを理解することで、より効果的なストレス管理が可能になります。
日本特有の労働文化:
- 長時間労働:月80時間以上の残業(過労死ライン)
- サービス残業:統計に現れない無給労働
- 有給休暇の未消化:取得率約50%(欧米は80-100%)
- プレゼンティーイズム:体調不良でも出勤する文化
日本の集団主義的文化がもたらすストレス:
- 同調圧力:「空気を読む」ことへのプレッシャー
- 恥の文化:失敗や弱さを見せることへの強い抵抗
- 建前と本音:真の感情を表現できないストレス
- 相互監視:常に他人の目を意識する緊張
文化的ストレスの具体例:
例:「迷惑をかけてはいけない」という価値観から、助けを求められない。「我慢は美徳」という考えから、ストレスを溜め込む。「出る杭は打たれる」を恐れて、自己主張ができない。
- 就職活動の過酷さ(新卒一括採用のプレッシャー)
- 非正規雇用の増加による将来不安
- 結婚・出産のタイミングの悩み
- SNS疲れと承認欲求
- 管理職のプレッシャー(板挟みストレス)
- 教育費の負担
- 親の介護(ダブルケア問題)
- 更年期による心身の変化
- 定年後の役割喪失
- 年金不安と老後資金
- 健康不安と医療費
- 社会的孤立
日本社会における性別役割分担意識がもたらすストレス:
- キャリアと出産の両立困難(M字カーブ問題)
- ワンオペ育児の負担
- 職場での性差別・セクハラ
- 「良妻賢母」プレッシャー
- 「一家の大黒柱」プレッシャー
- 感情表現の抑制(「男は泣くな」文化)
- 長時間労働の常態化
- メンタルヘルスケアへの偏見
今回は、ストレスの原因と個人差について詳しく解説しました。重要なポイントは:
- ストレッサーには外的要因と内的要因がある
- 遺伝、幼少期体験、現在の環境が個人差を生む
- ストレスには成長を促すものと有害なものがある
- 日本特有の文化的要因も考慮する必要がある
次回は、「慢性ストレスとHPA系の機能不全」について、長期的なストレスが心身に与える影響を詳しく解説します。
五反田ストレスケアクリニック院長
- ✓ 精神保健指定医
- ✓ 日本医師会認定産業医
- ✓ 産業保健法務主任者(メンタルヘルス法務主任者)
- ✓ 健康経営アドバイザー
大学病院から民間病院まで幅広い臨床経験を活かし、患者さんが安心して治療を継続できるよう、わかりやすい情報提供を心がけています。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の症状や状況に対する医学的アドバイスではありません。医療に関する決定は、必ず医師と相談の上で行ってください。本記事の情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当院は責任を負いかねます。
- Juruena MF, Bourne M, Young AH, Cleare AJ. Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis Dysfunction by Early Life Stress. Neuroscience Letters. 2021;759:136037. doi:10.1016/j.neulet.2021.136037.
- van Bodegom M, Homberg JR, Henckens MJAG. Modulation of the Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis by Early Life Stress Exposure. Frontiers in Cellular Neuroscience. 2017;11:87. doi:10.3389/fncel.2017.00087.
- Filetti C, Kane-Grade F, Gunnar M. The Development of Stress Reactivity and Regulation in Children and Adolescents. Current Neuropharmacology. 2024;22(3):395-419. doi:10.2174/1570159X21666230808120504.
- Koss KJ, Gunnar MR. Annual Research Review: Early Adversity, the Hypothalamic-Pituitary-Adrenocortical Axis, and Child Psychopathology. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines. 2018;59(4):327-346. doi:10.1111/jcpp.12784.
- Nicolaides NC, Kanaka-Gantenbein C, Pervanidou P. Developmental Neuroendocrinology of Early-Life Stress: Impact on Child Development and Behavior. Current Neuropharmacology. 2024;22(3):461-474. doi:10.2174/1570159X21666230810162344.
- Pervanidou P, Chrousos GP. Early-Life Stress: From Neuroendocrine Mechanisms to Stress-Related Disorders. Hormone Research in Paediatrics. 2018;89(5):372-379. doi:10.1159/000488468.
- Frodl T, O’Keane V. How Does the Brain Deal With Cumulative Stress? A Review With Focus on Developmental Stress, HPA Axis Function and Hippocampal Structure in Humans. Neurobiology of Disease. 2013;52:24-37. doi:10.1016/j.nbd.2012.03.012.
- Murphy F, Nasa A, Cullinane D, et al. Childhood Trauma, the HPA Axis and Psychiatric Illnesses: A Targeted Literature Synthesis. Frontiers in Psychiatry. 2022;13:748372. doi:10.3389/fpsyt.2022.748372.
- Hives BA, Beauchamp MR, Liu Y, Weiss J, Puterman E. Multidimensional Correlates of Psychological Stress: Insights From Traditional Statistical Approaches and Machine Learning Using a Nationally Representative Canadian Sample. PloS One. 2025;20(5):e0323197. doi:10.1371/journal.pone.0323197.
- Pang TY, Yaeger JDW, Summers CH, Mitra R. Cardinal Role of the Environment in Stress Induced Changes Across Life Stages and Generations. Neuroscience and Biobehavioral Reviews. 2021;124:137-150. doi:10.1016/j.neubiorev.2021.01.012.
- Sørensen JB, Lasgaard M, Willert MV, Larsen FB. The Relative Importance of Work-Related and Non-Work-Related Stressors and Perceived Social Support on Global Perceived Stress in a Cross-Sectional Population-Based Sample. BMC Public Health. 2021;21(1):543. doi:10.1186/s12889-021-10594-2.
- Shonkoff JP. Capitalizing on Advances in Science to Reduce the Health Consequences of Early Childhood Adversity. JAMA Pediatrics. 2016;170(10):1003-1007. doi:10.1001/jamapediatrics.2016.1559.
- Garner A, Yogman M. Preventing Childhood Toxic Stress: Partnering With Families and Communities to Promote Relational Health. Pediatrics. 2021;148(2):e2021052582. doi:10.1542/peds.2021-052582.
- Ma X, Kawakami A, Inui T. Impact of Long Working Hours on Mental Health Status in Japan: Evidence From a National Representative Survey. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2024;21(7):842. doi:10.3390/ijerph21070842.
- Takahashi M. Sociomedical Problems of Overwork-Related Deaths and Disorders in Japan. Journal of Occupational Health. 2019;61(4):269-277. doi:10.1002/1348-9585.12016.
- Lee H, Masuda T, Ishii K, Yasuda Y, Ohtsubo Y. Cultural Differences in the Perception of Daily Stress Between European Canadian and Japanese Undergraduate Students. Personality & Social Psychology Bulletin. 2023;49(4):571-584. doi:10.1177/01461672211070360.