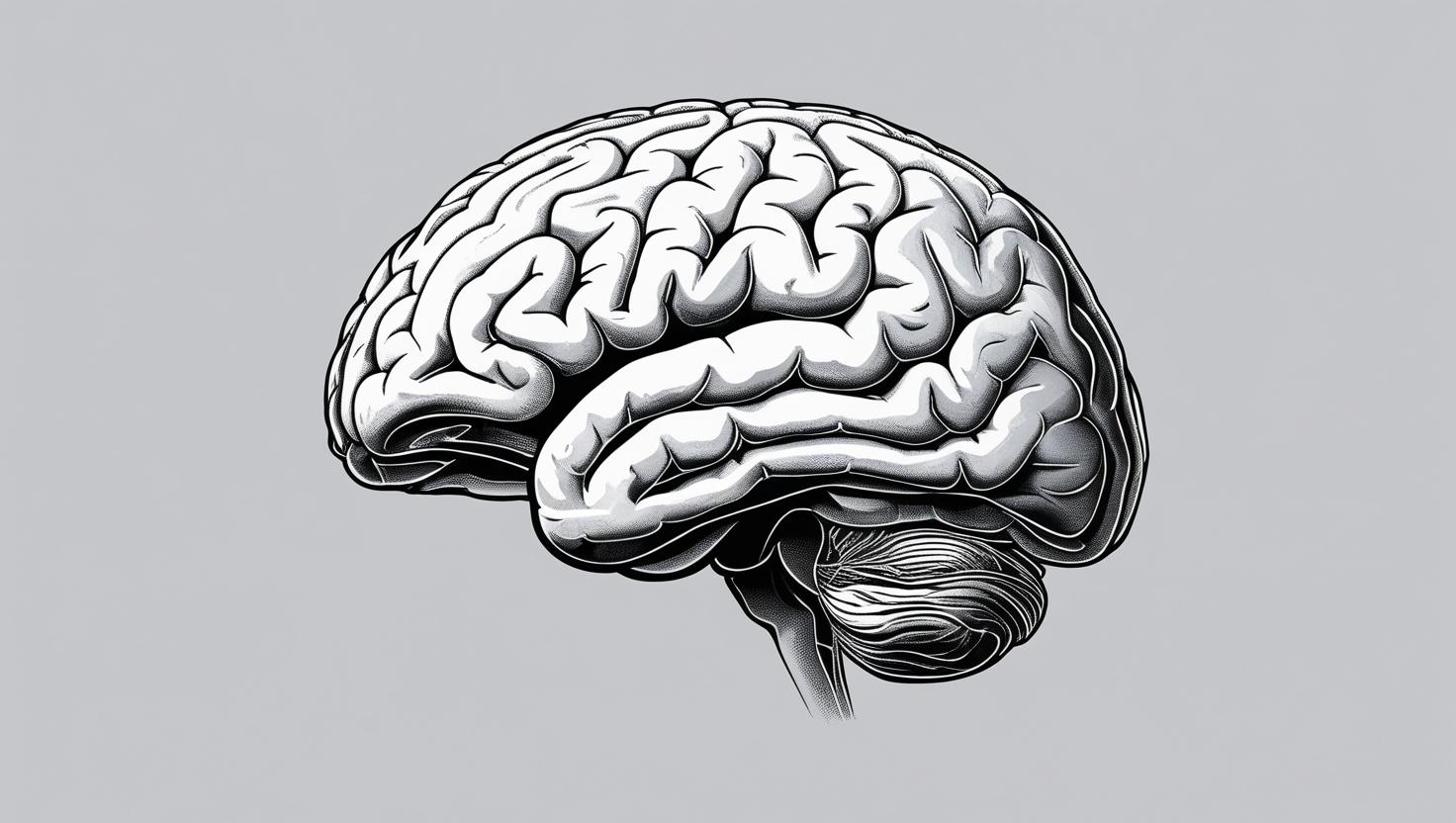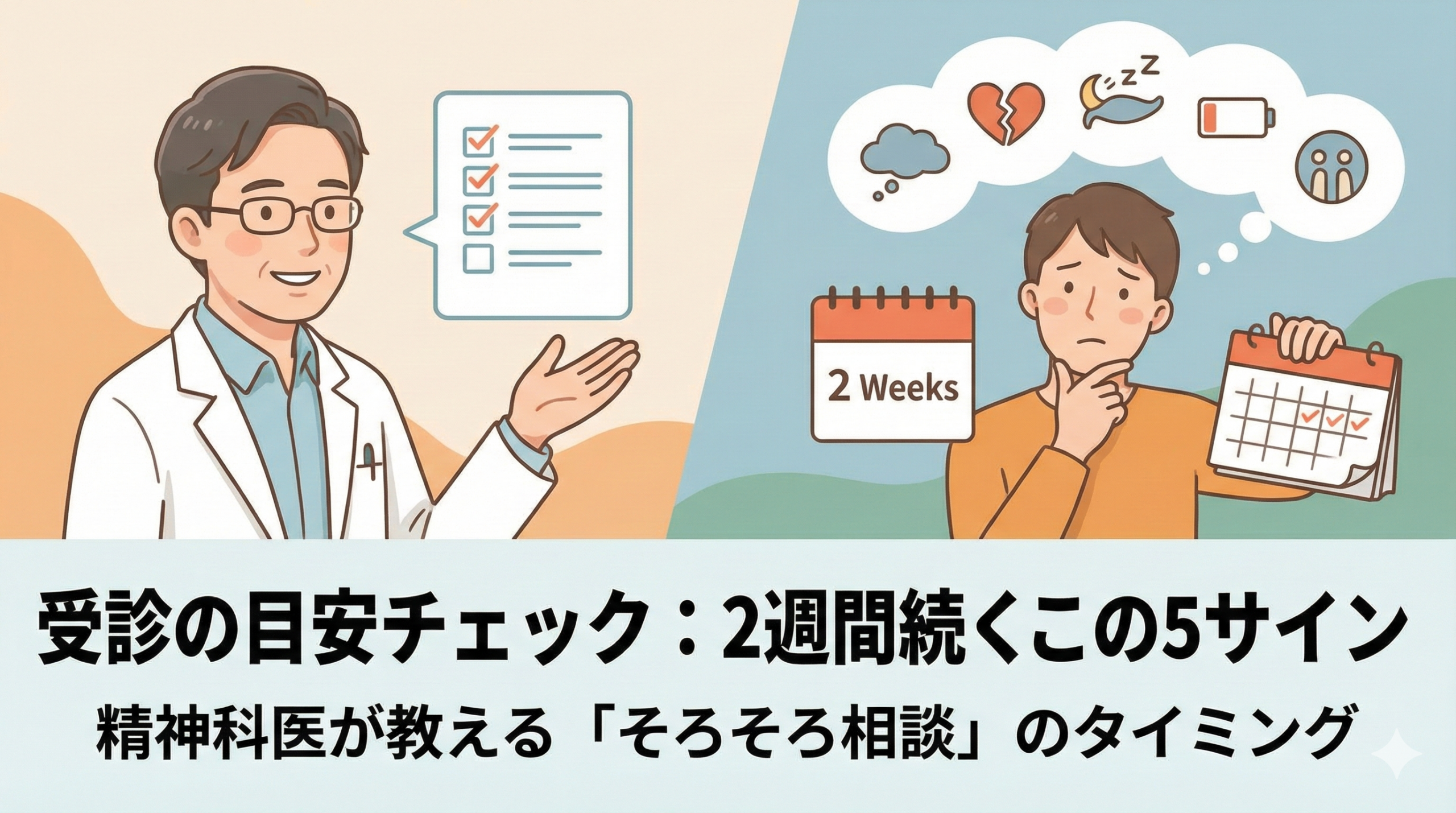2025年10月06日

「どの程度のストレスなら病院に行くべきか」「精神科は敷居が高い」「お金がかかりそう」-このような不安から、適切な支援を受けられずに苦しんでいる方が多くいます。日本には充実した医療制度と社会資源がありますが、その存在や活用方法が十分に知られていません。
精神科医として、また産業医として活動する中で、早期の適切な介入により多くの方が回復することを見てきました。今回は、日本の医療制度を最大限活用してストレスケアを行う方法を、具体的に解説します。
「まだ大丈夫」と我慢し続けることで、症状が重篤化するケースを多く見てきました。早期受診・早期治療が回復への近道です。
レッドフラグとなる症状

緊急性の高い症状(すぐに受診)
- 希死念慮:死にたい、消えたいという考え
- 自傷行為:リストカット、過量服薬
- 幻覚・妄想:現実にないものが見える、聞こえる
- 極度の興奮:制御できない怒り、暴力的衝動
- 意識障害:ぼーっとして反応が鈍い
緊急時は迷わず救急外来へ。精神科救急情報センター(東京都では
医療機関案内サービス 「ひまわり」
電話:03-5272-0303
聴覚障害者向け専用ファクシミリ※:03-5285-8080)や、
いのちの電話(0120-783-556)も利用できます。
早期受診が推奨される症状(2週間以上継続)
- 睡眠障害:入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒
- 食欲変化:著しい減退または過食
- 意欲低下:何もする気が起きない
- 集中力低下:仕事や家事でミスが増える
- 身体症状:原因不明の頭痛、腹痛、倦怠感
- 不安・パニック:動悸、息苦しさ、めまい
初診までの準備
限られた診察時間を有効に使うため、事前準備が重要です。
準備すること
初診時の持ち物チェックリスト:
□ 健康保険証
□ お薬手帳(他科の薬も含む)
□ 症状メモ(いつから、どんな症状)
□ 生活記録(睡眠、食事、活動)
□ 健康診断結果(あれば)
□ 紹介状(あれば)
□ 自立支援医療受給者証(持っている場合)
症状の伝え方
- 時系列で整理:いつから始まったか
- 具体的に:「眠れない」→「23時に布団に入るが2時まで眠れない」
- 生活への影響:仕事を休んだ日数、家事ができない程度
- きっかけ:思い当たるストレス要因
精神科と心療内科の違い
よく混同されますが、専門領域に違いがあります。
- 精神科
- うつ病、不安障害、統合失調症など精神疾患全般
- 薬物療法が中心
- 精神保健指定医がいる場合が多い
- 心療内科
- 心身症(ストレスによる身体症状)が専門
- 内科的アプローチも併用
- 軽度のうつ・不安も診療
働く人にとって、産業医は身近なメンタルヘルスの専門家です。しかし、その役割や活用法を知らない方が多いのが現状です。
ストレスチェック制度の実際
ストレスチェックの流れ
- 1. 実施:年1回、57項目の質問票
- 2. 結果通知:個人に直接(会社は見られない)
- 3. 高ストレス判定:該当者は医師面接の申出可能
- 4. 医師面接:産業医等による面接指導
- 5. 就業上の措置:必要に応じて配慮
ストレスチェックの結果は本人の同意なく会社に伝わりません。高ストレス判定でも、医師面接を申し出るかは本人の自由です。ただし、面接を受けることで適切な配慮を受けられる可能性があります。
産業医面談の効果的な受け方
面談で伝えるべきこと
- 業務上の負荷:残業時間、業務量、責任の重さ
- 職場の人間関係:上司・同僚との関係
- 身体症状:睡眠、食欲、体調の変化
- 希望する配慮:業務量調整、配置転換など
産業医ができること
産業医の役割:
✓ 健康相談(守秘義務あり)
✓ 職場環境の改善提案
✓ 業務内容・労働時間の調整助言
✓ 休職・復職の判定と支援
✓ 専門医療機関への紹介
× 診断書の発行(原則不可)
× 薬の処方(原則不可)
復職支援プログラム
メンタルヘルス不調で休職した場合の段階的な復職支援があります。
復職までのステップ
- 1. 療養期:十分な休養と治療
- 2. 回復期:生活リズムの確立
- 3. リワーク準備:復職プログラム参加
- 4. 試し出勤:短時間から段階的に
- 5. 復職:業務調整しながら本格復帰
日本には経済的負担を軽減する制度が整備されています。知らないために利用していない方が多いのが現状です。
自立支援医療(精神通院医療)
精神疾患の通院治療費が原則1割負担になる制度です。多くの精神疾患が対象となります。
対象となる疾患
申請方法
1. 診断書の取得:主治医に診断書を作成してもらう
2. 申請書類の準備:市区町村の窓口で申請書をもらう
3. 提出:市区町村の障害福祉課等に提出
4. 審査:1~2ヶ月で結果通知
5. 受給者証の交付:1年間有効(更新可能)
傷病手当金
病気で働けない期間の給与の約2/3が支給される健康保険の制度です。
支給条件
- 業務外の病気・ケガで療養中
- 仕事に就けない状態(医師の証明必要)
- 連続3日間の待期を満たしている
- 給与の支払いがない(または減額)
支給期間と金額
傷病手当金の概要:
支給期間:最長1年6ヶ月
支給額:標準報酬日額の2/3
例:月給30万円の場合、約20万円/月が支給
障害年金
精神疾患で日常生活や就労に支障がある場合、障害年金を受給できる可能性があります。
受給要件
- 初診日要件:初診日に年金加入していること
- 保険料納付要件:一定期間以上納付
- 障害状態要件:障害等級に該当
その他の支援制度
- 精神障害者保健福祉手帳:税金控除、公共料金割引など
- 生活困窮者自立支援制度:住居確保給付金、就労支援
- 生活福祉資金貸付:低利または無利子の貸付
- リワークプログラム:復職支援プログラム
適切な医療機関を選ぶことは、治療の成功の第一歩です。自分に合った医療機関を見つけるポイントを解説します。
医療機関の種類と特徴
診療所・クリニック
- メリット:アクセスしやすい、待ち時間が短い、継続的な関係構築
- デメリット:入院施設なし、検査設備が限定的
- こんな方に:軽度~中等度の症状、通院治療希望者
精神科病院
- メリット:入院可能、充実した検査設備、多職種チーム医療
- デメリット:待ち時間が長い、予約が取りにくい
- こんな方に:重度の症状、入院治療が必要な方
総合病院の精神科
- メリット:他科との連携、身体合併症対応可能
- デメリット:紹介状が必要な場合が多い
- こんな方に:身体疾患も併発している方
良い医療機関の見分け方
✓ 話をしっかり聞いてくれる(初診30分以上)
✓ 治療方針を丁寧に説明する
✓ 薬の説明が十分(効果と副作用)
✓ 質問しやすい雰囲気
✓ 予約が取りやすい
✓ スタッフの対応が良い
✓ 清潔で落ち着いた環境
オンライン診療の活用
コロナ禍以降、オンライン診療が普及しています。
オンライン診療のメリット
- 通院の負担軽減(移動時間・交通費)
- 待ち時間の短縮
- プライバシーの確保
- 感染リスクの回避
注意点
- 初診は原則対面診療が必要
- 処方できない薬がある
- 緊急時の対応に限界
- 通信環境の確保が必要
監修・執筆者
片山 渚 医師
五反田ストレスケアクリニック院長
- ✓ 精神保健指定医
- ✓ 日本医師会認定産業医
- ✓ 産業保健法務主任者(メンタルヘルス法務主任者)
- ✓ 健康経営アドバイザー
大学病院から民間病院まで幅広い臨床経験を活かし、患者さんが安心して治療を継続できるよう、わかりやすい情報提供を心がけています。
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の症状や状況に対する医学的アドバイスではありません。医療に関する決定は、必ず医師と相談の上で行ってください。本記事の情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当院は責任を負いかねます。