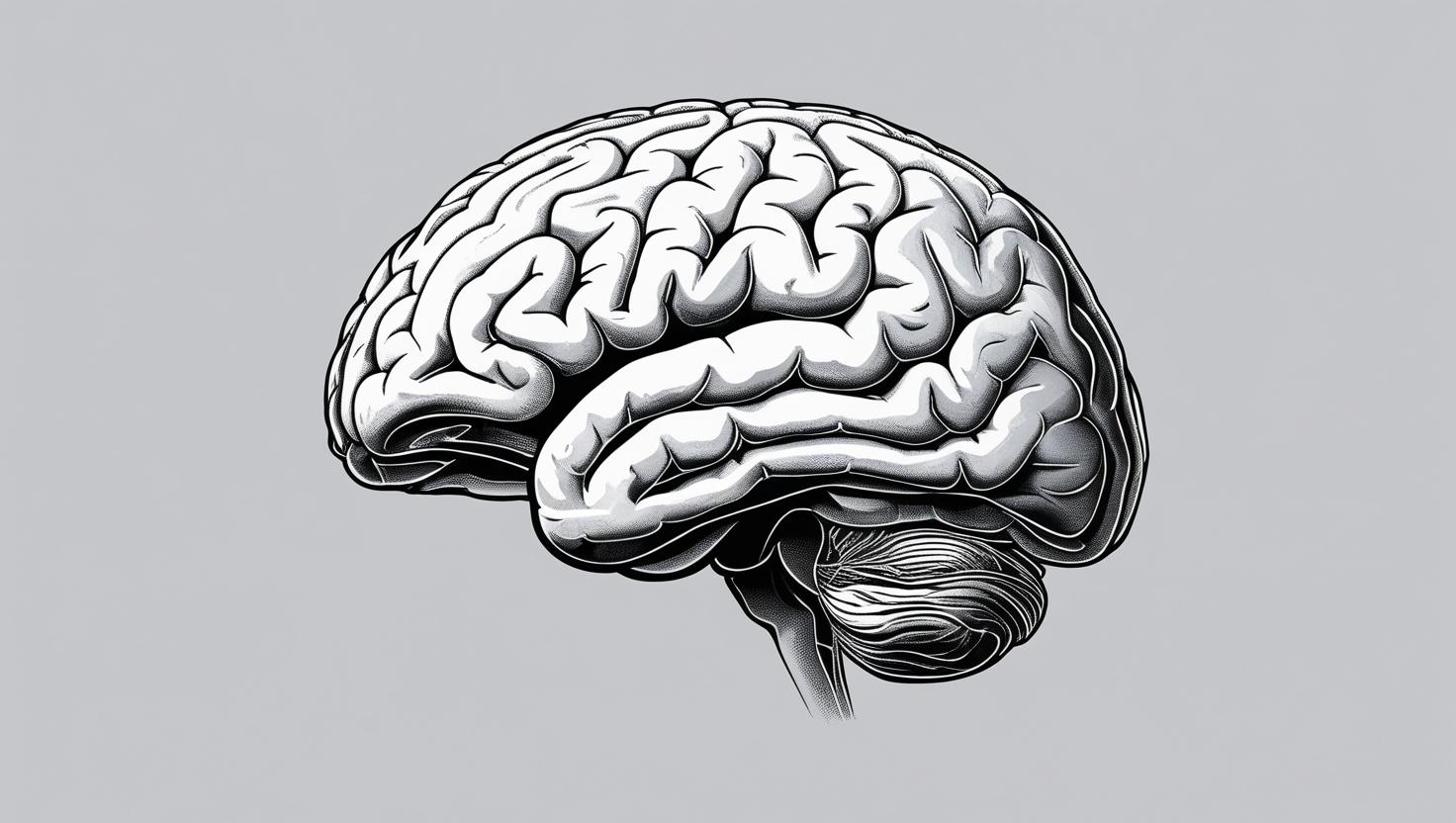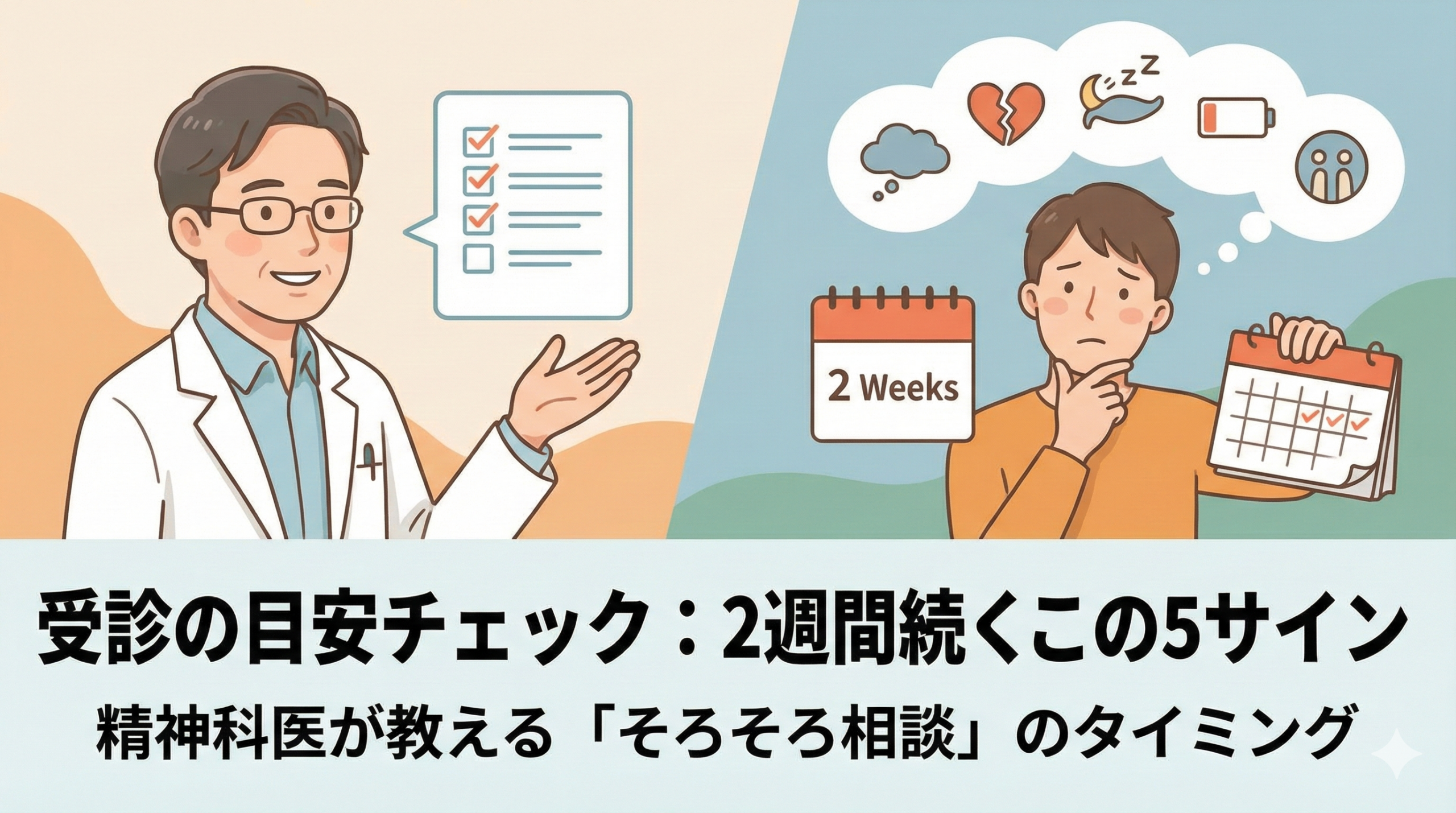2025年8月25日
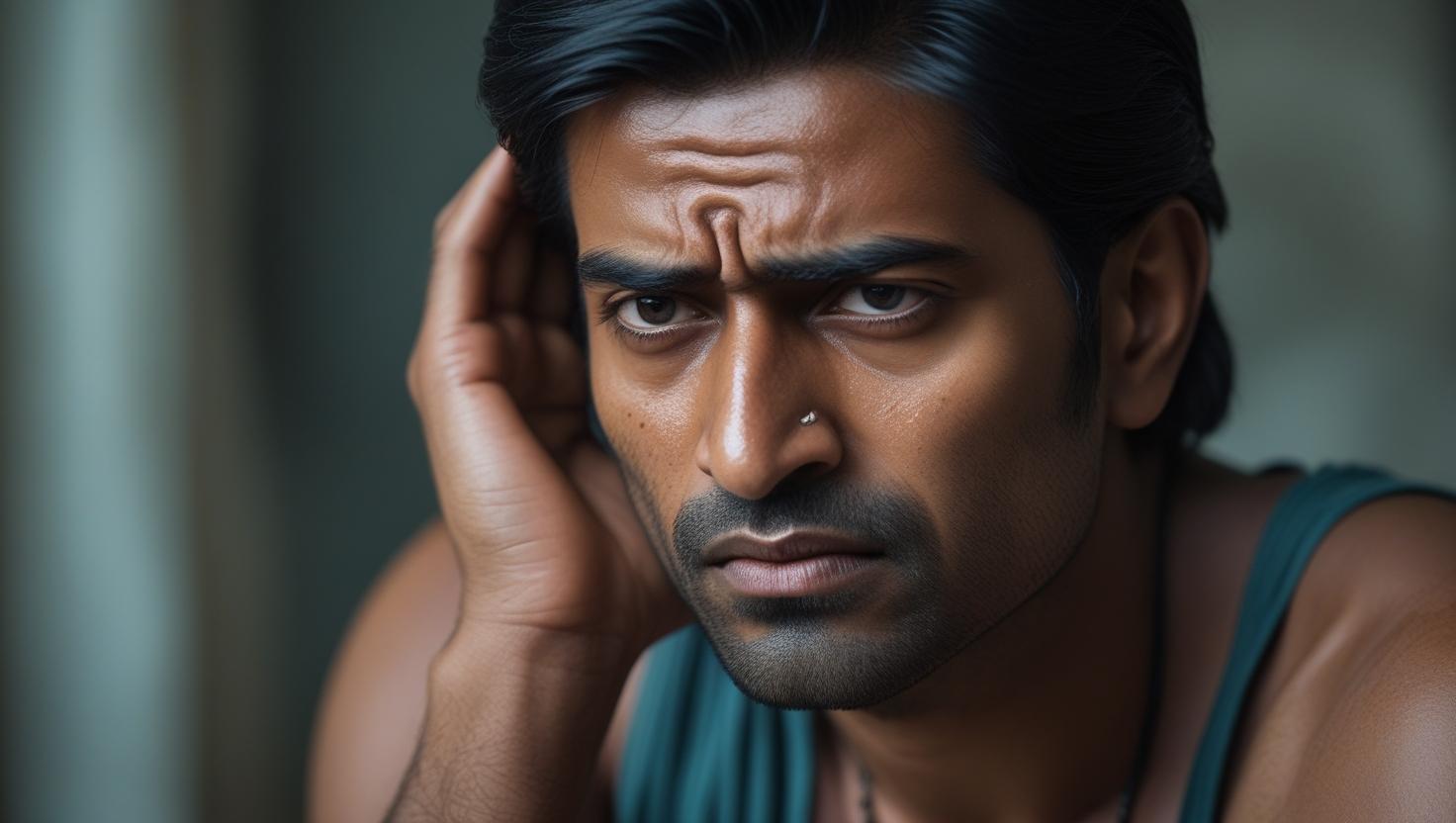
「最近、何をしても疲れが取れない」「ストレスが続いて、体調不良が慢性化している」-このような訴えで受診される患者さんが増えています。短期的なストレスは誰もが経験しますが、慢性的なストレスは身体のストレス反応システムであるHPA系に複雑な変化をもたらし、様々な健康問題を引き起こします。
今回は、慢性ストレスがHPA系にどのような変化をもたらし、それが心身にどう影響するのか、最新の研究知見を基に詳しく解説します。また、話題の「副腎疲労症候群」についても、医学的見地から正しい理解をお伝えします。
急性ストレスへの反応は生存に必要な適応的メカニズムですが、ストレスが長期化すると、HPA系は「適応的」から「不適応的」な状態へと移行します。重要なことは、この変化は画一的ではなく、ストレッサーの種類、強度、持続時間、個体差により多様な表現型を示すことです1,2。
HPA系の慢性的活性化の多様なパターン

慢性ストレスにおけるHPA系の変化は、単純な段階的進行ではなく、複数の異なる表現型として現れます1,2:
パターン1:持続的な過活動型(Hyperresponsive pattern)
- 基礎コルチゾールの上昇:日中の高値が持続
- 日内リズムの平坦化:夜間コルチゾールの上昇により振幅が減少
- CRHからAVPへのドライブシフト:視床下部の適応的変化5
- 副腎感受性の上昇:ACTHへの反応性増強
この表現型で見られる典型的な症状:
例:不眠(特に中途覚醒)、イライラ感、集中力低下、筋肉の緊張、頭痛、動悸、血圧上昇、代謝症候群のリスク増加
パターン2:低反応性型(Hyporesponsive pattern)
- ストレッサーへの反応減弱:特に心理的ストレスへの反応低下8
- 朝のコルチゾールピーク消失:覚醒反応(CAR)の減弱
- グルココルチコイド受容体の感受性変化:組織特異的な抵抗性
- 炎症マーカーの上昇:抗炎症作用の低下
パターン3:混合型・変動型
- 時期による変動:過活動と低反応の交代
- ストレッサー特異的な反応:身体的・心理的ストレスで異なる反応
- 性差による違い:女性では月経周期との相互作用9
HPA系の変化パターンは個人差が大きく、固定的な「段階」として進行するのではありません。ストレッサーの種類、遺伝的背景、早期逆境体験、性別などが反応パターンを決定します1,2,4。
分子・神経回路レベルでの変化
慢性ストレスは、HPA系の各レベルで複雑な分子的・回路的変化を引き起こします:
視床下部室傍核(PVN)における変化
- シナプス再編成
- 興奮性・抑制性シナプスの増加6
- GABA入力の樹状突起への再配置
- グルタミン酸/GABA比の変化10
- 神経ペプチドの変化
- CRHからAVP優位へのシフト5
- 共発現パターンの変化
前頭前野からの制御系の変化
- 前頭前野→扁桃体分界条床核→PVN回路
- 樹状突起スパインの減少7
- シナプス伝達効率の低下
- HPA抑制機能の減弱
グルココルチコイド受容体システムの変化
- 受容体発現の変化
- MR/GR比の変化4
- 組織特異的な発現調節
- エピジェネティックな修飾
- FKBP5遺伝子のメチル化変化
- NR3C1(GR遺伝子)のプロモーター領域メチル化4
コルチゾールは「ストレスホルモン」と呼ばれますが、適切な量では生命維持に不可欠です。しかし、慢性ストレスによるコルチゾール分泌パターンの変化(高値持続または低反応性)は、全身の様々なシステムに影響を与えます3,5。
身体的影響:多臓器への影響
1. 心血管系への影響
- 血圧上昇:交感神経亢進、ナトリウム再吸収増加
- 動脈硬化の進展:内皮機能障害(NO産生抑制)、低度慢性炎症、血管平滑筋増殖11,12
- 急性心血管イベント:心筋梗塞・脳卒中リスク上昇、プラーク不安定化12
- ストレス心筋症:たこつぼ心筋症、精神的ストレス誘発性心筋虚血(MSIMI)11
- 不整脈:不整脈閾値の低下
研究データ:
例:毛髪コルチゾール/コルチゾン(長期ストレス指標)の高値は心血管疾患と関連し、標準危険因子とは独立した関連を示す(メタ解析:SMD 0.48)。大規模疫学統合解析でも成人期ストレスはCVD発症・予後悪化と関連12,15。
2. 代謝系への影響
- インスリン抵抗性:2型糖尿病リスク上昇16,18
- 中心性肥満:内臓脂肪蓄積の促進
- 脂質異常症:中性脂肪上昇、HDLコレステロール低下17
- メタボリックシンドローム:日内コルチゾール異常や朝コルチゾール高値と関連16,17,18
3. 免疫系への影響
コルチゾールは本来、抗炎症作用を持ちますが、慢性的な調節異常は複雑な影響をもたらします:
- 免疫抑制と感染感受性:細胞性免疫の抑制により感染リスク上昇14,16
- 慢性低度炎症の持続:GR抵抗性による炎症制御不全(IL-6、TNF-α、CRP上昇)14,19
- 心血管・代謝疾患への関与:慢性炎症が病態進展に寄与12,14
- アレルギー・自己免疫:影響は疾患・個体差により多様(一様な因果関係は限定的)14,16,19
4. 消化器系への影響
- 腸管バリア機能低下:腸管透過性亢進、炎症の波及16,19
- 過敏性腸症候群(IBS):機能性消化管障害の悪化16,19
- 腸内細菌叢の変化:ディスバイオシス10
- 消化性潰瘍:主要因はNSAIDs/H.pylori(ストレス単独の因果は限定的)16,19
5. 骨・筋肉系への影響
- 骨粗鬆症:骨吸収促進・骨形成抑制による骨密度低下16,20
- 筋量・筋力低下:筋蛋白分解亢進によるサルコペニア様変化16,20
- 慢性疼痛:中枢感作、炎症性サイトカインの関与
- 線維筋痛症:HPA系の多様な表現型(高値/低値両方)が存在、一義的な高コルチゾール病態ではない16,20
慢性高コルチゾール曝露は、心血管・代謝リスクの上昇、免疫抑制と慢性炎症の併存、腸管機能変化、骨・筋萎縮をもたらし得ます。これらはアロスタティック負荷(allostatic load)の中核であり、行動・環境・薬理的介入による是正が心代謝リスク低減の候補となります12,15-19。
精神的影響:脳機能への影響
慢性的なHPA系の調節異常は、脳の構造と機能に影響を与えます。これらの変化は個体差が大きく、ストレッサーの種類や併存因子により効果量は変動します。

1. 海馬への影響
- 構造的変化:樹状突起の退縮、シナプス可塑性の変化9
- 成人海馬神経新生の抑制:歯状回での新生ニューロン減少9
- 容積変化:うつ病や早期逆境体験で海馬容積低下が報告(ただし個体差・併存因子により効果量は可変)9
- 記憶機能への影響:宣言的記憶、空間記憶の低下9
- 興奮毒性:グルタミン酸過活動が機序として示唆(ヒトでの神経細胞死の直接証拠は限定的)9
2. 前頭前皮質への影響
- 機能的変化:fMRI研究で背外側・腹内側前頭前皮質の機能低下6
- 実行機能の低下:注意、作業記憶、情動調節の障害6
- 構造的変化:樹状突起スパインの減少(動物研究)1
- 扁桃体制御の低下:HPA系への抑制機能減弱
3. 扁桃体への影響
- 反応性の増強:情動刺激への過敏性上昇6,9
- 情動記憶の固定化促進:ストレス関連記憶の強化6
- 前頭前野-扁桃体バランス:「前頭前野機能低下・扁桃体亢進」パターン6,9
4. 臨床的高コルチゾール例での認知機能
サブクリニカルクッシング症候群(自律性コルチゾール分泌)の研究では:
- 作業記憶の低下:コルチゾール非抑制度と相関
- 視空間機能の低下:慢性高コルチゾールの臨床的裏付け
5. 精神疾患のリスク
慢性ストレスとHPA系機能不全は、うつ病、PTSD、双極性障害、精神病性障害のリスクと関連します。ただし、リスクの程度は疾患、集団、測定方法(早期逆境体験、毛髪コルチゾール等)により大きく異なり、画一的な倍率での表現は適切ではありません7,8。HPA過活動やデキサメタゾン非抑制は、認知機能低下や精神病発症リスクの指標となり得ます7,8。
HPA系機能不全を正確に診断することは、適切な治療方針を立てる上で重要です。診断は主にコルチゾール測定と機能検査が中心となります。
1. コルチゾール測定法
コルチゾール測定はHPA系機能評価の基本的手法ですが、それぞれに特徴と限界があります10。
血中コルチゾール
- 測定時間:日内変動が大きいため、早朝(8時前後)の測定が推奨される
- 判定基準:カットオフ値は検査法ごとに異なるため、施設ごとの基準値に従う10
- 利点:正確、他の検査と同時実施可能
- 欠点:採血ストレスの影響、来院が必要
唾液コルチゾール
- 測定時間:深夜や起床時の測定がCushing症候群やHPA軸評価に有用
- CAR(Cortisol Awakening Response):起床後の上昇を評価
- 利点:非侵襲的、自宅で採取可能、日内変動評価
- 注意点:サンプル採取・保存条件に注意が必要10
唾液コルチゾール採取の注意点:
例:採取30分前から飲食・歯磨き・喫煙を避ける。採取時は専用綿棒を2分間口に含む。採取後は冷蔵保存し、3日以内に検査機関へ。
24時間尿中遊離コルチゾール
- 適応:長期的なコルチゾール分泌量の指標
- 利点:24時間の総分泌量を評価
- 限界:腎機能や尿量の影響を受けやすい10
2. 機能検査
機能検査はHPA軸機能不全の診断において標準的な手法です10。
ACTH刺激試験
- 標準法:250μg コシントロピン静注
- 判定基準:30または60分後の血中コルチゾール<18μg/dL(<500nmol/L)で副腎不全を示唆10
- 適応:副腎不全の診断
デキサメタゾン抑制試験(DST)
- 方法:1mg投与翌朝のコルチゾール測定
- 判定:コルチゾール抑制不良でCushing症候群を示唆
- 適応:Cushing症候群のスクリーニング10
CRH刺激試験
- 適応:ACTH依存性Cushing症候群の鑑別
- 注意:日常診療での頻用は限定的10
HPA軸機能不全の診断は、コルチゾール測定と機能検査が中心です。各検査法には特徴と限界があるため、臨床症状と合わせて総合的に判断する必要があります10。
3. バイオマーカー(補助的評価)
以下のバイオマーカーは診断補助的役割を持ちますが、HPA軸機能不全の直接的な診断根拠とはなりません6,8,10:
- DHEA-S:副腎皮質機能の指標として有用、特にコルチゾール値が判定困難な場合の補助診断に推奨8,10
- 炎症マーカー(CRP、IL-6、TNF-α):ストレス反応の評価には有用だが、診断的意義は限定的6
- 酸化ストレスマーカー(8-OHdG、MDA):研究的使用に留まる
- 心拍変動(HRV):自律神経機能評価には有用だが、HPA軸機能不全の診断的意義は限定的6
4. 臨床評価ツール(ストレス評価)
- PSS(Perceived Stress Scale):主観的ストレス評価
- 職業性ストレス簡易調査票:職場ストレスのスクリーニング
- K6/K10:心理的苦痛のスクリーニング
- ACE質問票:幼少期逆境体験の評価8
これらは客観的なHPA軸機能障害の診断とは必ずしも一致しないことに注意が必要です。
「副腎疲労症候群(Adrenal Fatigue Syndrome)」という概念は、1998年にJames Wilson博士によって提唱されました。しかし、「副腎疲労」は医学文献で認識された診断名ではなく、内分泌専門学会(米国、欧州、日本)でも診断概念として採用されていません11。
副腎疲労症候群の概念と問題点
Wilson氏による定義:
- 慢性ストレスにより副腎が「疲弊」する
- コルチゾール分泌が低下
- 起床困難、塩分渇望などが生じる
- 標準的な検査では正常範囲
医学的な問題点
この概念が認められない理由:①解剖学的・内分泌学的根拠が不十分、②症状が非特異的、③唾液コルチゾールのみでの診断は妥当性に欠ける、④サプリメント中心の治療に一貫したエビデンスがない、⑤HPA異常は多様で疾患特異性に乏しい、⑥Wilsonのモデルに再現性がない11,15。
実際の病態:HPA系調節異常
「副腎疲労」とされる症状の背景にある実際の病態は、副腎の「疲労」ではなく、以下の複合的な調節異常です11,15:
- HPA軸の調節障害
- 軽度の低コルチゾール血症
- 日内変動の減弱
- 負のフィードバックの過敏化
- ストレッサーへの反応性低下
- グルココルチコイド受容体の感受性変化11,15
- 概日リズムの乱れ
- 他の内分泌異常
- 甲状腺機能異常
- 性腺機能異常
- 成長ホルモン軸の異常
- 自律神経調節異常11,15
これらの変化は慢性疲労症候群(ME/CFS)や線維筋痛症でも報告されますが、個体差が大きく一様ではありません11,14,15。
慢性疲労の鑑別診断
慢性疲労を主訴とする場合、以下の疾患を系統的に除外する必要があります14:
重要な鑑別診断:
- 内分泌疾患:原発性副腎不全(アジソン病)、甲状腺機能低下症、糖尿病
- 感染症:慢性感染症、HIV、肝炎
- 精神疾患:うつ病、不安障害、身体表現性障害
- 睡眠障害:閉塞性睡眠時無呼吸症候群
- 血液疾患:貧血(鉄欠乏、ビタミンB12欠乏)
- 自己免疫疾患:全身性エリテマトーデス、関節リウマチ
- その他:ME/CFS、線維筋痛症、悪性腫瘍
推奨される医学的アプローチ
慢性的な疲労とストレス関連症状に対する適切なアプローチ11,14:
- 包括的な医学的評価
- 詳細な病歴聴取(発症様式、増悪因子、随伴症状)
- 系統的な身体診察
- 適切な血液検査(CBC、甲状腺機能、電解質、肝腎機能、炎症マーカー)
- 朝コルチゾール測定(必要時は動的試験を検討)
- 必要に応じた画像検査
- エビデンスに基づく治療
- 認知行動療法(CBT):ME/CFSでも有効性が示される11,14
- 段階的活動療法(適切な活動調整)
- マインドフルネスベースストレス低減法
- 睡眠衛生指導
- 栄養バランスの改善
- 併存疾患に対する適切な薬物療法
- 心理社会的サポート
慢性疲労症候群(ME/CFS)や慢性疲労に対して、ステロイド補充は推奨されません。副腎不全が明確に診断された場合のみ、ホルモン補充療法の適応となります11。
まとめ:慢性ストレスへの正しい理解と対処
今回は、慢性ストレスとHPA系機能不全について詳しく解説しました。重要なポイントは:
- 心血管系: 持続的ストレス/高コルチゾールは血圧上昇、内皮機能障害、低度炎症・交感神経亢進・凝固亢進を介して動脈硬化進展、プラーク不安定化、急性イベント(心筋梗塞・脳卒中)リスク上昇に関与します。精神的ストレスは不整脈閾値低下やMSIMI、たこつぼ心筋症のトリガーとなり得ます4,12
- 代謝系: 慢性高コルチゾールはインスリン抵抗性、中心性肥満、脂質異常(TG↑/HDL↓)、高血糖を促し、2型糖尿病・メタボリックシンドロームのリスク上昇と関連します5,12,13
- 免疫系: コルチゾールの免疫抑制により感染感受性が上昇しうる一方、慢性曝露やGR抵抗性の出現で低度慢性炎症が持続し、心血管・代謝疾患の病態に関与します4,6
- 消化管: 慢性ストレス/高コルチゾールは腸管バリア機能低下、腸内細菌叢変化、機能性消化管障害(IBS)悪化と関連するエビデンスがありますが、潰瘍は主としてNSAIDs/ヘリコバクターが主要因で、ストレス単独の因果は限定的です3,6
- 筋骨格系: 慢性グルココルチコイド作用は骨吸収促進・骨形成抑制により骨粗鬆症リスクを上げ、筋蛋白分解亢進により筋量・筋力低下(サルコペニア様)を来します3
次回は、「ストレス管理の実践:エビデンスに基づく介入法」について、具体的な対処法を詳しく解説します。
参考文献
参考文献
- Herman JP, McKlveen JM, Ghosal S, et al. Regulation of the Hypothalamic-Pituitary-Adrenocortical Stress Response. Comprehensive Physiology. 2016;6(2):603-21.
- Miller GE, Chen E, Zhou ES. If It Goes Up, Must It Come Down? Chronic Stress and the Hypothalamic-Pituitary-Adrenocortical Axis in Humans. Psychological Bulletin. 2007;133(1):25-45.
- Russell G, Lightman S. The Human Stress Response. Nature Reviews Endocrinology. 2019;15(9):525-534.
- Kivimäki M, Steptoe A. Effects of Stress on the Development and Progression of Cardiovascular Disease. Nature Reviews Cardiology. 2018;15(4):215-229.
- Kivimäki M, Bartolomucci A, Kawachi I. The Multiple Roles of Life Stress in Metabolic Disorders. Nature Reviews Endocrinology. 2023;19(1):10-27.
- O’Connor DB, Thayer JF, Vedhara K. Stress and Health: A Review of Psychobiological Processes. Annual Review of Psychology. 2021;72:663-688.
- Agorastos A, Chrousos GP. The Neuroendocrinology of Stress: The Stress-Related Continuum of Chronic Disease Development. Molecular Psychiatry. 2022;27(1):502-513.
- Juruena MF, Bourne M, Young AH, Cleare AJ. Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis Dysfunction by Early Life Stress. Neuroscience Letters. 2021;759:136037.
- Frodl T, O’Keane V. How Does the Brain Deal With Cumulative Stress? A Review With Focus on Developmental Stress, HPA Axis Function and Hippocampal Structure in Humans. Neurobiology of Disease. 2013;52:24-37.
- Karaca Z, Grossman A, Kelestimur F. Investigation of the Hypothalamo-Pituitary-Adrenal (HPA) Axis: A Contemporary Synthesis. Reviews in Endocrine & Metabolic Disorders. 2021;22(2):179-204.
- Cleare AJ. The Neuroendocrinology of Chronic Fatigue Syndrome. Endocrine Reviews. 2003;24(2):236-52.
- Kuckuck S, Lengton R, Boon MR, et al. Long-Term Glucocorticoids in Relation to the Metabolic Syndrome and Cardiovascular Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Internal Medicine. 2024;295(1):2-19.
- Ortiz R, Kluwe B, Lazarus S, Teruel MN, Joseph JJ. Cortisol and Cardiometabolic Disease: A Target for Advancing Health Equity. Trends in Endocrinology and Metabolism. 2022;33(11):786-797.
- Sandler CX, Lloyd AR. Chronic Fatigue Syndrome: Progress and Possibilities. Medical Journal of Australia. 2020;212(9):428-433.
- Strahler J, Skoluda N, Rohleder N, Nater UM. Dysregulated Stress Signal Sensitivity and Inflammatory Disinhibition as a Pathophysiological Mechanism of Stress-Related Chronic Fatigue. Neuroscience and Biobehavioral Reviews. 2016;68:298-318.
監修・執筆者
片山 渚 医師
五反田ストレスケアクリニック院長
- ✓ 精神保健指定医
- ✓ 日本医師会認定産業医
- ✓ 産業保健法務主任者(メンタルヘルス法務主任者)
- ✓ 健康経営アドバイザー
大学病院から民間病院まで幅広い臨床経験を活かし、患者さんが安心して治療を継続できるよう、わかりやすい情報提供を心がけています。
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の症状や状況に対する医学的アドバイスではありません。医療に関する決定は、必ず医師と相談の上で行ってください。本記事の情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当院は責任を負いかねます。